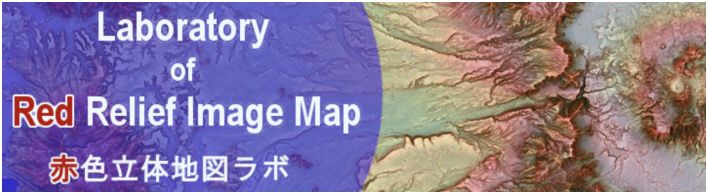先端研の研究領域
技術コラム第一回
階段で考える地理空間情報
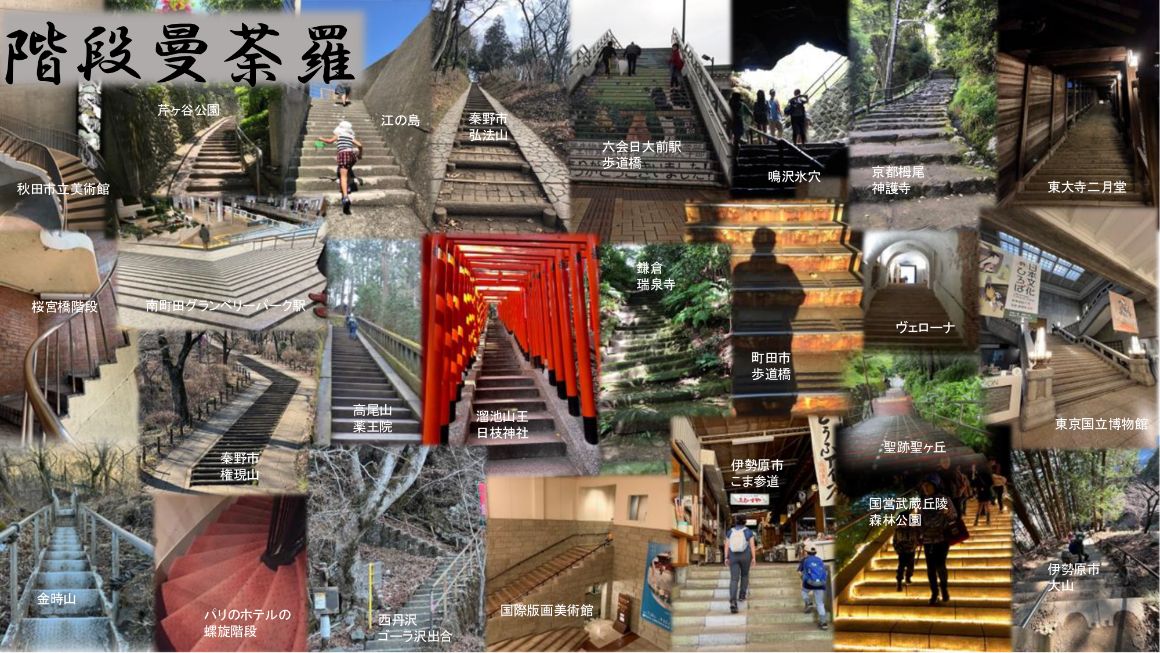
階段を上るのが好きです。
新型コロナの流行期に体重が2割増えたことから、手軽な運動として階段上りを始めました。毎日最低50階を登ることを目標にしています。日常に利用する階段はたくさんあります。駅の階段、公園の階段、職場のビルの階段、集合住宅の階段。休日に山を歩けばそこは階段天国です。
スマートフォンが万歩計になる仕組み

毎日どれぐらい階段を上ったかを記録するのに便利なのはスマホの健康アプリです。私はiOSの「Appleヘルスケア」アプリ1)を使っています。このアプリは、健康や運動の情報をまとめて管理することができます。標準搭載で歩数も自動でカウントしてくれるので、これでスマホを万歩計として使っている人も多いでしょう。3mの垂直移動を歩いて上ったときに1階上ったとカウントされます。階段でなくても坂道を上ってもOK。ただしあまりにもゆっくり階段を上った場合や、緩やかな傾斜の坂道を上った場合はカウントされないようです。
さて、なぜスマートフォンが万歩計になるかというと、3軸加速度センサが搭載されているからです。着地した時の振動を解析して歩数を推定しています。またなぜ標高差が計測できるかというと、気圧センサが組み込まれているからです。スマートフォンには、3軸の加速度・角速度・磁力センサ、そして気圧計が内蔵されています。位置を直接計測するGNSSセンサも搭載されています。最新機種にはLiDAR(距離センサ)も搭載されています。カメラも強力な光学センサです。それらを活用する様々な計測アプリもあります。スマートフォンは大変優秀な地理空間情報複合センサなのです。
測量の歴史
古来測量では、長さと角度を計測することにより地理空間情報を取得してきました。水準測量では鉛直(水平)方向を基準に高さ(の差)を計測します。古くはヘレニズム時代のエラトステネスが、夏至の太陽の南中高度の差を用いて地球の大きさを推定したように、重力方向や天体を基準として人類は測量を行ってきました。
時間も地理空間分野では重要な計測対象です。18世紀になって⾼精度な機械式時計(クロノメーター)が発明されると、太陽の南中時刻の差から経度差を精確に測定できるようになりました2)。光波測距儀やGNSSでは、光速を基準にナノ秒単位の時間の計測を行い、電磁波の到達時間を利⽤して距離や位置を測定しています。スマートフォンで現在位置を知るために使われているGNSSは、現代の精密測量において必要不可欠の技術です。
現代の測量で必須な加速度・角速度センサ

加速度や角速度を計測できるようになると、それを積分することによって三次元的な姿勢や移動量が正確に計測できるようになりました。この技術は身近なところではゲーム機のモーションセンサに利用されていますが、空中写真測量・航空レーザ測量・車載レーザ測量といった測量でも必須のセンサです。加速度計は重力加速度も計測していますが、重力加速度を精密に計測すると、地球の重力分布がわかるだけでなく、等重力ポテンシャル面(ジオイド)の決定にも利用できます。国土地理院が実施した精密な航空重力測量の成果に基づき、令和7年4月1日から日本の新しい標高体系がはじまりました3)。
スマートフォンには、精度の違いはあるものの、地理空間計測に用いられる様々なタイプのセンサが搭載されています。その恩恵を受けながら今⽇も私は階段を上ります。私たちの職場は、高畑勲監督のスタジオジブリ映画「平成狸合戦ぽんぽこ」で知られる多摩丘陵のど真ん中にあります。いくら地⾯を削ったり埋めたりしたところで、⾕や尾根といった自然の地形が残されています。そんな場所には坂道があり、階段があります。
最近の一押しの階段は川崎市多摩区にある生田配水池展望台への階段。段数218段・高度差約40m!未知なる階段を求めてスマホ片手に散歩に出かけましょう!

- 1) https://www.apple.com/jp/health/ (accessed 2025/6/23)
- 2) D.ソベル.「経度への挑戦:1秒に欠けた四百年」, 角川文庫.
- 3) https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html (accessed 2025/6/23)
著者紹介
織田 和夫研究室(個人研究室)室長
織田 和夫(おだ かずお)

PROFILE
- 所属学会
- 日本写真測量学会、地理情報システム学会・日本リモートセンシング学会
- プロフィール
- 京都大学理学部地球物理学科卒。1988年アジア航測(株)入社。1994~1996年カーネギーメロン大学客員研究員。2018~2022年日本デジタル道路地図協会。日本写真測量学会常務理事・編集委員長(2024年9月現在)。論文博士(工学・東京大学)、技術士(応用理学)、測量士、空間情報総括監理技術者。平成13年度測量技術奨励賞、平成16年度日本写真測量学会学会賞受賞。専門は写真測量・画像処理。趣味は野鳥観察・軽登山・リコーダー。